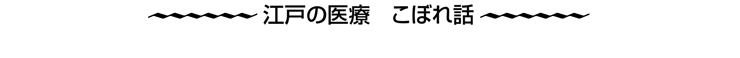解説 お江戸の科学
江戸時代の医者
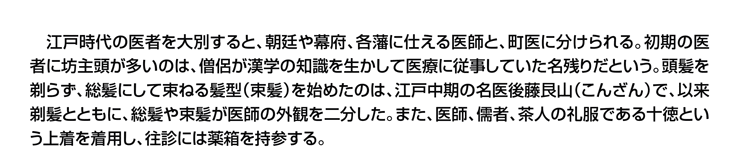
江戸時代の医者を大別すると、朝廷や幕府、各藩に仕える医師と、町医に分けられる。初期の医者に坊主頭が多いのは、僧侶が漢学の知識を生かして医療に従事していた名残りだという。頭髪を剃らず、総髪にして束ねる髪型(束髪)を始めたのは、江戸中期の名医後藤艮山(こんざん)で、以来剃髪とともに、総髪や束髪が医師の外観を二分した。また、医師、儒者、茶人の礼服である十徳という上着を着用し、往診には薬箱を持参する。
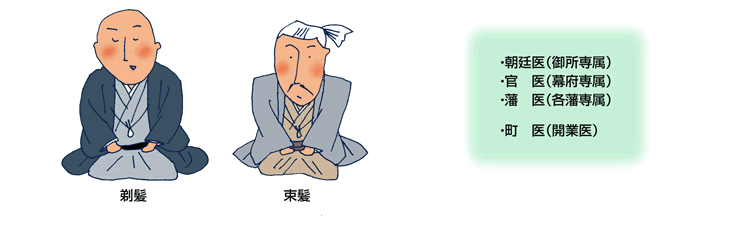
剃髪 束髪
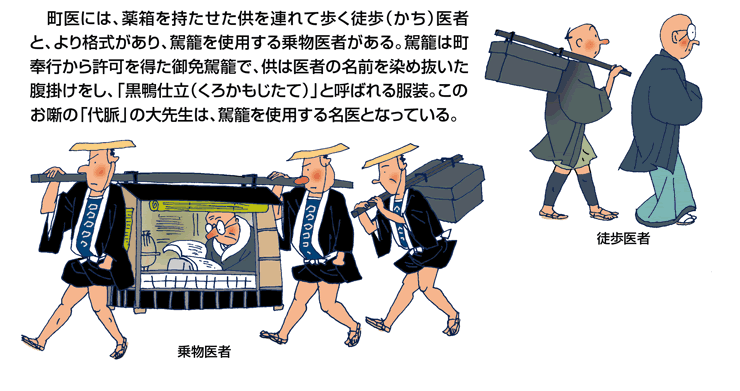
町医には、薬箱を持たせた供を連れて歩く徒歩(かち)医者と、より格式があり、駕籠を使用する乗物医者がある。駕籠は町奉行から許可を得た御免駕籠で、供は医者の名前を染め抜いた腹掛けをし、「黒鴨仕立(くろかもじたて)」と呼ばれる服装。このお噺の「代脈」の大先生は、駕籠を使用する名医となっている。
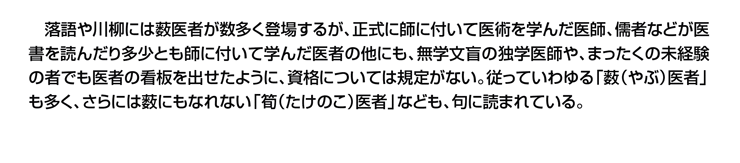
落語や川柳には薮医者が数多く登場するが、正式に師に付いて医術を学んだ医師、儒者などが医書を読んだり多少とも師に付いて学んだ医者の他にも、無学文盲の独学医師や、まったくの未経験の者でも医者の看板を出せたように、資格については規定がない。従っていわゆる「薮(やぶ)医者」も多く、さらには薮にもなれない「筍(たけのこ)医者」なども、句に読まれている。
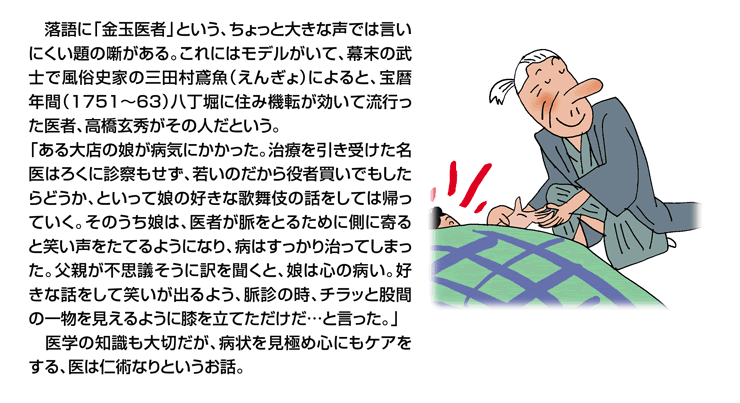
落語に「金玉医者」という、ちょっと大きな声では言いにくい題の噺がある。これにはモデルがいて、幕末の武士で風俗史家の三田村鳶魚(えんぎょ)によると、宝暦年間(1751〜63)八丁堀に住み機転が効いて流行った医者、高橋玄秀がその人だという。 「ある大店の娘が病気にかかった。治療を引き受けた名医はろくに診察もせず、若いのだから役者買いでもしたらどうか、といって娘の好きな歌舞伎の話をしては帰っていく。そのうち娘は、医者が脈をとるために側に寄ると笑い声をたてるようになり、病はすっかり治ってしまった。父親が不思議そうに訳を聞くと、娘は心の病い。好きな話をして笑いが出るよう、脈診の時、チラッと股間の一物を見えるように膝を立てただけだ…と言った。」 医学の知識も大切だが、病状を見極め心にもケアをする、医は仁術なりというお話。
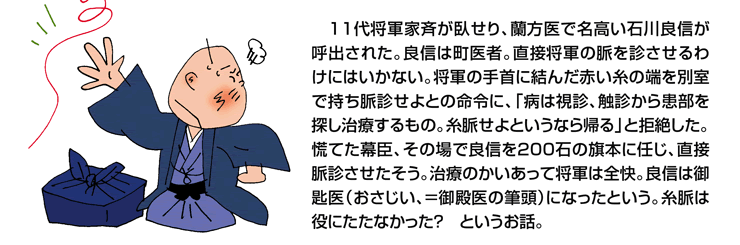
11代将軍家斉が臥せり、蘭方医で名高い石川良信が呼出された。良信は町医者。直接将軍の脈を診させるわけにはいかない。将軍の手首に結んだ赤い糸の端を別室で持ち脈診せよとの命令に、「病は視診、触診から患部を探し治療するもの。糸脈せよというなら帰る」と拒絶した。慌てた幕臣、その場で良信を200石の旗本に任じ、直接脈診させたそう。治療のかいあって将軍は全快。良信は御匙医(おさじい、=御殿医の筆頭)になったという。糸脈は役にたたなかった? というお話。