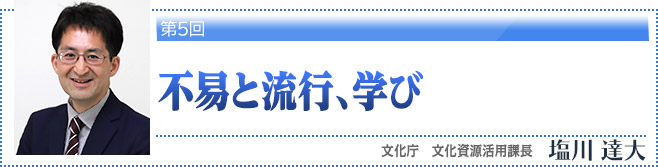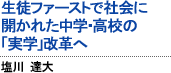スタートアップ、起業の意義については国や研究者の論文等でもスタートアップの意義については最近当たり前のように語られております。「社会人」となる学生のキャリアデザインや就職活動でも、就職先で職業人としての人生を全うすることは、昔のように当然の前提ということはなくなってきております。転職を想定している学生は増えてきている、このことは皆様にとっても違和感ないと思います。
ここで、今から15年ぐらい前を思い出してください。当時、7・5・3現象という言葉がありました。新規学卒就職者が、就職後3年以内で離職する割合について、中卒だと約7割、高卒だと5割、大卒だと3割という状況を指すものでした。一旦離職すると正社員化が厳しくなる。だからこそキャリア教育が大事だという見解や、高校生の就職活動における「一人一社制度」がミスマッチを生じているといった見解等もありますが、これらの前提として共通するのは、同じ勤務先で、正社員として、長期にわたり勤務することが望ましいという価値観です。
なお、最新(令和3年3月卒業者)の新規学卒就職者の就職後3年での離職率をみると、中卒51%、高卒 38%、大学 35% となっています(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html)。
しかしながら、これらのデータから5・4・4現象という新語ができて人口に膾炙されるでもなく、離職率の動向へ耳目をひくことは小さくなっております。このように干支が一回りするぐらいの時の流れで、仕事観、勤労への価値観が様変わりしていることが分かります。
2020年度に開設した、とある大学では、全員起業、目標就職率ゼロを目標に掲げたりしています。最終的な1期生の進路は起業10%、就職82%、進学・その他8%ということですが、それでも組織に身を置かず、卒業後すぐに起業を選ぶ人が10%いるわけです。少なくともこの大学の学生さんにとっては、終身雇用が無条件に肯定的にとらえられていた時代は過去のものと言えそうです。
このように仕事についての価値観も行動も変わってきておりますが、大人はどうでしょうか。先生も保護者も、若い世代に対して、従来の価値観で接しておりませんでしょうか。
総論は良いが、各論になると話は違うという言動はないでしょうか。
キャリア研究の分野で有名なサニー・ハンセンさんは、統合的生涯設計・Integrated Life Plan理論を提唱する中、4つのLと6つの重要課題を提示しております。4つのLは、人生の4つの役割としてLove、Labor、Leisure、Learningを掲げ、これらが独立することなくつながることで、キャリアが豊かになるというものです。そして、統合的なキャリアプランとしての具体の重要課題として、以下の6つを提示しております。
- ① グローバルな状況を変化させるためになすべき仕事を探す
- ② 人生を意味ある全体像のなかに織り込む
- ③ 家庭と仕事の間を結ぶ
- ④ 多元性と包括性を大切にする
- ⑤ 個人の転機と組織の変革に共に対処する:チェンジ・エージェント
- ⑥ 精神性、人生の目的、意味を探求する
このように、米国人のハンセンさんはチェンジ・エージェントという言葉を使っておりますが、OECDは教育政策でエージェンシーの大事さを提唱しております。エージェンシー、すなわち、「自ら考え、主体的に行動して、責任をもって社会変革を実現していく力」を有する者がエージェントと考えても間違いではないと思います。そして、こうしたエージェント、エージェンシーというテーマは、我が国の学習指導要領が目指す、思考力・判断力・表現力の育成と合致すると言ってもよさそうです。
今回、何を申し上げたかったかといえば、以下の三点です。
- ①不易と流行という言葉、学校関係者もよく引用する言葉ですが、この不易と流行について、何を不易、何を流行と捉えるかについて、我々大人は過去の経験そのものを安易に不易ととらえないように気を付ける必要があるということ
- ②子どもたちには、大人である自分の価値観を強要することにつなげないことに気を付ける必要があるということ
- ③グローバルで変化が速い社会だからこそ、我々大人が子どもと同じようにチェンジ・エージェントの姿勢を有していく必要があるのではないかということ
以上三つの思いです。
これらに気を付けることで、大人にとっては、人生百年時代の、自らの意味ある人生づくりにつながりますし、子どもの学びの場づくりとしては、将来主体的に意味ある人生づくりに寄与することにつながると思います。学校教育関係者は、過去の常識が非常識になり得ることを自覚し、自らの価値観を自ら疑うことを出発点にすることで、子ども第一、エージェンシーづくりを大事にした学びの場づくりにつながるのではというのは言い過ぎでしょうか。
過去の知見を知恵と錯覚することなく、むしろ知見を知恵に昇華し、それによって真の不易と流行に基づく教育を進めていきたいものです。カリキュラムオーバーロードといった言葉も、10年前には新聞に出ることなど考えられなかったと思います。教科と特別活動のバランスや、対面とオンラインのバランス、教育課程内での学びの在り方、これらすべてについて不易と流行をしっかり考えていく必要があると思います。