TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
シリーズ「教育大変動」を語る
第9回
児童生徒の「意欲低下」はなぜ起きる?
規範意識の乱れは大人側の問題
- 古川:
- しつけに関する国際比較は意外な結果でした。保護者から「ちゃんとあいさつをしなさい」「テレビを見すぎだからやめなさい」「友だちと仲良くしなさい」「ウソをつかないようにしなさい」という4項目すべてについて言われている子が、米英独韓いずれの国よりも日本は少ないですね(図1)。
- 衞藤:
- さらに、「学校で子どもに社会のルールやマナーについて教えてほしい」という保護者が非常に多いことも特徴です(図2)。これは、子どもの問題のように見えて、実は大人の側の問題です。自分たちの文化なり規範なりを、次の人たちに伝えていくことを怠っているのです。世代間の文化の伝承も断絶し、地域での支え合いもなくなり、孤立化したなかでの子育てという状況も生まれました。
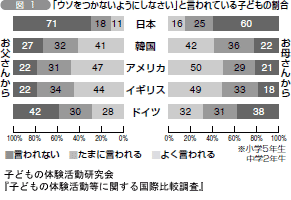
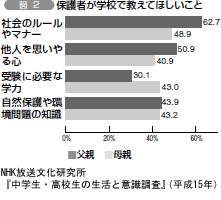
※図1~8は、すべて答申「青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促す方策について」(中間まとめ)による。- 古川:
- なぜそうなったのでしょうか?
- 衞藤:
- 戦後社会の中で、ロッキード事件に代表されるような汚職事件や大学紛争などで、価値感や規範の体系がかなり崩れたと思いますね。拠り所となる共通の基盤がなくなることで、「自分流」がすべてになった。
海外では、ウソをつかないとか、人には親切にしなさいとか、人に危害を加えないというようなことは子どものときにたたき込まれています。ロバート・フルガム(Robert Fulghum)という人が、「All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten〔. 人生に必要な知恵は、すべて幼稚園の砂場で学んだ〕」と唱えています。これらの規範は全部幼稚園のときに教わり、そこで身についているはずということです。 - 古川:
- 小中学生の道徳観・正義感は、自然体験の数が多いほど身につき、学習意欲も高まる、といったデータもあります。
- 衞藤:
- 体験に基づいて学ぶという部分があるということですね。そのとき、一人で自然体験をするのではなくて、集団遊びをすることが前提だと思います。
自然というのは、一筋縄ではいかない厳しい面がありますから、一人では乗り越えられない場面に置かれることで、友だちと共同し知恵を出し合って挑戦するよい訓練になるということではないでしょうか。


-
- »研究領域とテーマ
- »メッセージ
- »「教育大変動」を語る










