TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
シリーズ「教育大変動」を語る
第12回
能動的に学習する授業と教師のフォローが学力の高い子どもを作る!
課題を行わせた後のフォローが学力を作る
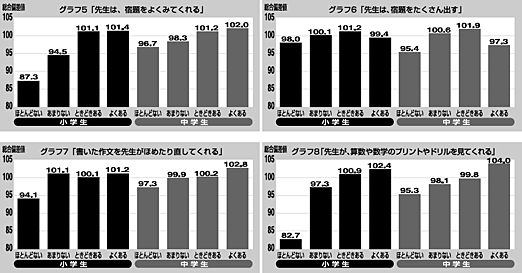
- 古川:
- グラフ5、グラフ7~9のように、子どもひとり一人に対応した指導を行っているかどうかでも、明らかな学力差が出ています。特にグラフ8の「算数や数学のプリントやドリルを見てくれる」では、小学校で大きな学力の違いが出ていますが。
- 山崎:
- これらの項目は、授業後のアフターケアが必要であることを示しています。教えっぱなしではなく、その後の指導をこまめに行うことが大事だということですね。
- 古川:
- しかし、宿題の量は多すぎると逆効果になるようですが。(グラフ6)
- 山崎:
- 宿題は出す量ではなくて、結果を見てあげられるかどうかが重要です。30人の子どもがいれば、すべて読んでコメントを付けて返す。先生方はとても大変だと思いますが、見ることが効果を上げるのです。
- 古川:
- グラフ10「放課後に先生が分からないことを教えてくれる」では、「よくある」という子は、逆に学力が低い傾向にありますが?
- 山崎:
- 「よくある」と答えた子どもは、「元々学力が低く、授業を十分に理解できていないから、放課後も指導を受ける必要がある」という因果関係になっていることが推測できます。「学力が低いために放課後の指導を受けている」のであって、「放課後の指導を受けると学力が低くなる」ということではないと思います。
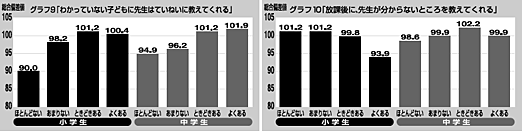


-
- »研究領域とテーマ
- »メッセージ
- »「教育大変動」を語る










