TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
シリーズ「教育大変動」を語る
第11回
児童の学力を左右する「社会的背景」とは?
「新たなモラル」が引き起こす学力低下
- 古川:
- 「新たなモラル」が引き起こす学力低下
- 耳塚:
- 給食費を払わない家庭があるとか、子どもの遅刻や欠席で先生が家庭に電話をかけると、親から「何で学校に行かなきゃいけないのか」と言われ、先生方が困ることがあると言います。しかし、これはある意味で当然の反応なのではないでしょうか。
学校の勉強を一生懸命やって報われるのは、一部の高学歴のホワイトカラー層であって、将来それ以外の生き方を選ぶ子どもやその親にとっては重要ではない。だとしたら適当に手を抜いて何がいけないのか?これは、従来のモラルの低下ではなく、新たなモラルが出来つつあるということだと思います。 - 古川:
- このような家庭環境に起因する学力格差があるなかで、現場の先生たちに出来ることは何でしょうか?
- 耳塚:
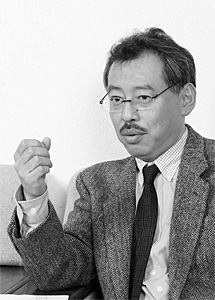 難しいですね。なぜなら、個人情報保護の関係で、子どもが家に帰ったらどういう生活をしているか、どういう状況に置かれているかを教員が把握することが困難になっています。また、把握していたとしても、家庭の状況に学校があれこれ意見することは、なかなか出来ないことですね。
難しいですね。なぜなら、個人情報保護の関係で、子どもが家に帰ったらどういう生活をしているか、どういう状況に置かれているかを教員が把握することが困難になっています。また、把握していたとしても、家庭の状況に学校があれこれ意見することは、なかなか出来ないことですね。
ただ言えることは、底上げ指導をていねいに、諦めずに継続するということでしょうか。学校以外の教育に依存できない子どもたちは、学校でしか学力を向上させることはできません。学校が手を引いたらおしまいです。保護者に対しては、何が重要か理解してもらうために働きかけるということ。これには特効薬はありません。
正直なところ、家庭環境の影響から起こる問題は教育問題ではなく、社会問題だという気がします。ですから経済格差を緩和する政策も教育政策以上に重要です。
現場の先生にとって、今いちばん大切なのは、こういうことも含めて、現場で何が起きているのかを、先生方ご自身が声に出していかれることだと思います。


-
- »研究領域とテーマ
- »メッセージ
- »「教育大変動」を語る










