TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
シリーズ「教育大変動」を語る
第10回
教員のストレスは、残業減では解決しない!
「多忙」はストレスの直接原因ではない!
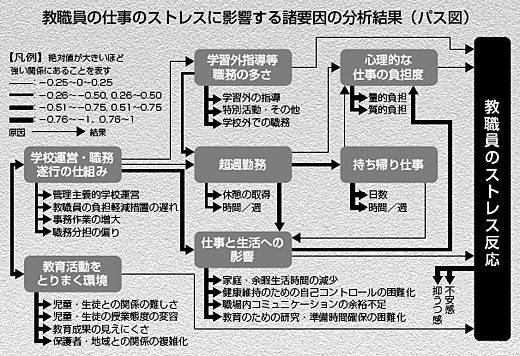
- 古川:
- まず、パス解析図の読み方を教えてください。
- 酒井:
- 矢印の方向が、因果関係の原因と結果との関係を表しています。両側に矢印が付いている部分は因果関係ではなくて、相互に影響し合う要因だということです。また太いものほど、強い関係にあるということを示しています。
- 古川:
- このパス解析図からどのようなことが読み取れるのでしょうか?
- 酒井:
- よく言われる「仕事による多忙」、ここでは「超過勤務」や「持ち帰り仕事」は、ストレスの直接の原因になっていないということですね。
その両方は二つの方向を向いています。一つは「仕事と生活への影響」、もう一つは「心理的な仕事の負担度」です。大事なことは超過勤務や持ち帰り仕事が原因となって仕事や生活に影響を与えている、さらにそれが原因となって仕事や生活への影響が及んでいることです。
私たちの仮説では、超過勤務自体が直接ストレスを生じさせる原因となる負荷だと考えていました。しかし、超過勤務が直接引き起こしているのは、家庭にいる時間や余暇時間が減る、睡眠や休息をとるための時間が少ない、時間がなくて職場内でのコミュニケーションがとりづらい、授業のための十分な研究や準備時間が確保できないなどの問題でした。
そういう問題を介して、初めて抑うつのようなストレス反応に影響するという二段階のメカニズムがあるということがわかったわけです。 - 古川:
- 超過勤務をしていても、「仕事と生活への影響」や「心理的な仕事の負担」が、何らかの手段で軽減されていれば、超過勤務をしていること自体はストレスにはならないということでしょうか?
- 酒井:
- 「ならない」と言い切ることは難しいですね。しかし、単に「残業時間を減らしましょう」で済む話ではないということははっきりしています。
例えば、児童生徒との関係が円滑にいかないとか、保護者との関係が難しいと感じている先生たちのサポートをどうするか、授業だけでなく校務などを含めて学校の中での教員の役割をどう位置づけ、業務の負荷を分散していくか、というところが解決していかないと、超過勤務だけを解決しようとしてもストレスは軽減しないということですね。


-
- »研究領域とテーマ
- »メッセージ
- »「教育大変動」を語る










