TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
シリーズ「教育大変動」を語る
第9回
児童生徒の「意欲低下」はなぜ起きる?
運動能力低下への歯止め
- 古川:
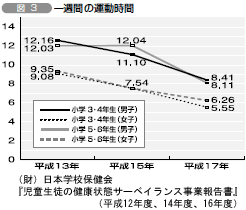 運動時間が減り(図3)、戸外で遊ぶ子どもの割合も低くなっています(図4)。
運動時間が減り(図3)、戸外で遊ぶ子どもの割合も低くなっています(図4)。- 衞藤:
- いまの子は習い事があったり、塾に行ったり、一人ひとりスケジュールが違うので、小学生でもスケジュール調整をしないとなかなか子ども同士で遊べないといった現実があります。一緒に遊ぶためには、多くの努力をしないといけないわけです。
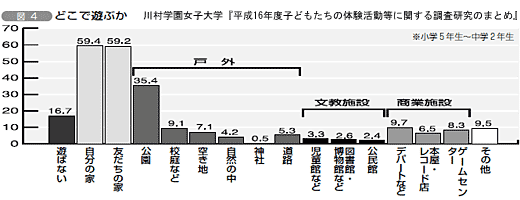
- 古川:
- 体力も低下しています。走る(50m走)、跳ぶ(立ち幅跳び)、投げる(ボール投げ)、握る(握力)、といった能力が20年間で確実に下がっていますね。(図5・6)
- 衞藤:
- 「体力・運動能力調査」は、昭和39年の東京オリンピックがあった年から毎年行っています。最初の10年はおしなべて向上傾向、次の10年は横ばい、最近20年は低下傾向が出ています。
ところが平成14、15年あたりから、13歳女子の50m走や13歳男女で持久力の数値が向上し、歯止めがかかった傾向が見えるところもあるのです。子どもの体力低下が言われ始めて10年近く経ちますが、その間にキャンペーンや体育を含めて外遊び、運動に親しむ機会の提供も行なっていますから、多少成果が出ていると私は考えています。 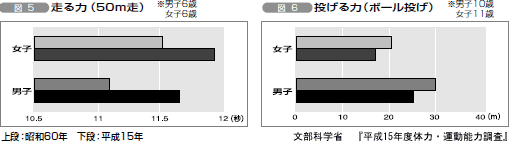


-
- »研究領域とテーマ
- »メッセージ
- »「教育大変動」を語る










