TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
シリーズ「教育大変動」を語る
第9回
児童生徒の「意欲低下」はなぜ起きる?
メディア提供側の対応
- 古川:
- 情報メディアに関しても新たな事態が起きています。なかでも、テレビやビデオの視聴時間は、米英独韓のそれぞれの国と比較しても大変長く(図7)、また自由時間はテレビを見て過ごすという子どもが71.9%にのぼるという現実は何を意味するのでしょうか?(図8)
- 衞藤:
- これは、特に生まれてすぐの赤ちゃんにとってはとても大きな問題です。心が発達する赤ちゃんの時期に、親が直接コミニュケーションを取らず、テレビやビデオに子育てをさせていると、笑わないとか、言葉が出ないなど、自閉症に近い状態になることがあります。テレビ漬けを止めると、表情が出て来て言葉を喋り出すんです。
アメリカの小児科学会は、2歳まではテレビやビデオは見せるべきではないと提言していますし、日本の小児科学会も平成16年に同様の発言をしています。
また、別の調査では、12歳になっても「人は死んでも生き返る」と思っている子どもたちがたくさんいるという結果が出ています。これは、TV番組やゲームなどの影響だと思われます。表現の自由もありますが、メディアを提供する側も、子どもたちの発達に与える影響を理解して、適切な対応をとることが必要だと思います。 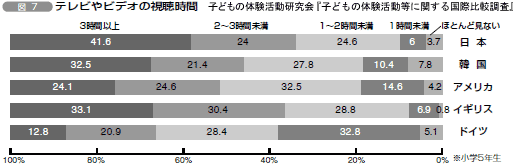
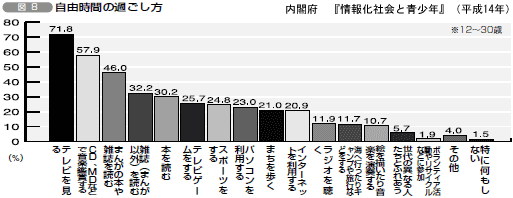


-
- »研究領域とテーマ
- »メッセージ
- »「教育大変動」を語る










