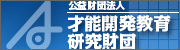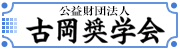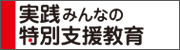角替弘規(桐蔭横浜大学教授)
おわりに
日本の子どもの理科の学力は世界でもトップクラスとされる一方で、近年では子どもの「理科離れ」が問題視されている。「理科離れ」が進む中においてなお、理科が好きな子どもとは、いかなる子どもなのか。どのような保護者のもとでどのような育てられ方をしてきた子どもなのだろうか。それとも、家庭や保護者とは何ら関係なく、単に子ども自身の持って生まれた特性によって理科好きであるかどうかが左右されるのであろうか。この調査はこうした疑問に端を発している。
第1章で明らかになったのは、保護者の職業や保護者の教育経験が、子どもの理科に対する選好傾向に影響しているということである。職業(今回の調査では父親の職業)別でみると、「生産工程・運輸従事者」と「専門技術系職員」の子どもに「理科がとても好き」という子どもが多く見られた。保護者の教育経験から見ると、父母ともに理系分野で学んでいた子どもの方が「理科がとても好き」と答える割合が多かった。また保護者の学歴別にみると、父母ともに大卒である場合、理科の成績が「とても良い」子どもの割合が高く、子どもの理科的な活動も活発である傾向が見受けられた。一方保護者の経済的所得別に検討してみると、所得の高さと子どもの理科好きとの関係は明確ではなかった。ただし理科の成績について見ると、所得の高い家庭の子どもの方が成績が良い傾向は見受けられた。したがって理科が好きかどうかということと、理科の成績の良し悪しは、単純には結び付かないと言えそうである。以上のことから子どもが理科好きであるかどうかは、その子どもの性格や個人的特性だけに依拠するわけではない。つまりその子どもを取り巻く家庭や大人によって、理科の選好傾向が異なってくる可能性が強く示された。
第2章では、家庭における理科的な活動への取り組みの状況を探った。その結果、保護者の教育経験や教育観などが、理科的な活動に積極的に取り組むかどうかに影響を与えていることが分かった。全体としては多くの家庭で子どもを大学段階まで進学させたいと考えている中で、特に男子に対して、そして保護者が大学以上の学歴を取得している場合にはその期待が特に強くなっていることが明らかとなった。また子どもの学習に積極的に関与していこうとする傾向を持つ家庭においても、子どもに高い教育期待をかけている傾向が見られた。こうした家庭環境の中で「理科」の学習が、いわば教育戦略の一環として位置づけられていると思われる。第1章における見地と重複するが、保護者が理系分野での教育経験を持っているかどうか、そして保護者が駆使できる「文化的資源」の違いによって、子どもの理科に対する興味・関心を引き出すことに対するコミットメントの違いが見受けられた。子どもの学習に積極的にかかわろうとする「学習関与志向」の家庭では、理科的な知識と情報の取得にウェイトが置かれがちであり、「多様な活動経験」を重視する家庭では知識よりも体験そのものにウェイトが置かれ、子どもの興味関心を多様に広げていく手段として「理科」を位置づけていると推測された。
とは言え、「理科好きな子ども」にはやはり何らかの共通した特性が見られるのではなかろうか。この疑問について検討した第3章では、個々の子どもの細かい性格というよりも、それらを導く特性、つまり「論理的・計画的」に物事を分析していこうとする特性や、「好奇心旺盛で行動力がある」といった特性を持った子どもに理科を好む傾向が見受けられた。さらに、全体としては男女のジェンダーの違いが見られ、女子よりも男子において理科好きの傾向が見受けられた。子どものジェンダーによって親の教育期待が異なる傾向にあることは第2章においても示されているところであり、興味深い。そして家庭においては保護者が子どもの理科的な活動に自発的にかかわっていくことの重要性が指摘されている。以上のように、各章における様々な側面についての分析結果から見て、結局のところ、子どもの学びがいかにあるのかということは、子ども単独の力や能力といったものによって決定されるのではなく、その子どものそばにいる大人、とりわけ保護者との関わりの中で決まってくるということを示唆していると言えるだろう。
ところで今回の調査で得られた結果を改めて捉えなおしたときに、全般的な傾向として小学生は「理科好き」という傾向にあることをもっと大事に考える必要があるだろう。保護者についても理科という教科を重要な教科であると認識しているし、日頃の生活の中で子どもと接する場合も、理科的な事柄を多少なりとも意識している様子がうかがえた。こうした小学生の傾向が、中学生になると反転してしまうことは、大変残念なことである。しかしながら、小学校の理科と中学校の理科では、同じ「理科」であっても随分と異なることに注意する必要があるだろう。教育段階が上がるにつれて、理科は分野ごとに細分化が進んでいく。思い返してみれば、「物理」は得意だが「化学」は苦手といった人も少なくないのではないだろうか。その意味では、中学校段階とはいえ、ある程度の細分化が進む「理科」は同一教科の中でも得意不得意が併存しうる教科と言える。そうした細分化が進む前段階として、あらゆる分野をひとつにまとめた小学校の「理科」という教科に対して、多くの小学生が「好き」と感じていることは極めて重要であろう。無論、中学校以上の段階においても、生徒が小学生の時に理科に対して持っていた興味と関心を損なわないための工夫は必要であるが、理科に対する積極的な興味関心を当初から持っているということは、大きなアドバンテージのはずである。したがって、小学生の多くが理科好きであるという傾向を保たせていくための持続的な取り組みが大人の側に求められる。そして理科の選好傾向を持続させてゆくには、恐らく、学校だけの取り組みでは不十分であろう。理科に対する興味関心や理科の成績に対して、家庭の属性が少なからず影響を与えていることについては留意すべきであり、経済的な不平等とそれに起因すると思われる問題については何らかの形で補われるべきであると考えるが、家庭における子どもたちへの保護者からの働きかけがより重要な意味を持つと思われる。家庭は、学校の理科で得た知識を、実生活における身の回りの経験の中で確かめる場として有用である。そして、そこから生じる疑問を学校に持ち帰ることにより、学校での学びがより豊かなものになるであろう。このような循環を実現することで、理科に対する興味と関心を持続させていくことができるのではないだろうか。

-
- »はじめに
- »第1章 保護者の属性から見た子どもの「理科好き」
- はじめに
- 1.子どもの「理科的な活動」への取り組みと「理科好き」
- 2.保護者の職業と子どもの「理科好き」
- 3.保護者の所得と子どもの「理科好き」
- 4.保護者が受けてきた教育と子どもの「理科好き」
- おわりに
- »第2章 子どもの教育に対する家庭の方針 -理科的な活動に対する保護者のかまえに着目して-
- はじめに
- 1.家庭におけるしつけ・教育の方針
- (1)日常生活に関わるしつけの方針
- (2)子どもの学習への関与志向
- (3)子どもの教育達成への期待
- (4)多様な活動経験の提供に対する構え
- 2.理科的な活動に対する保護者の構え
- (1)理系分野に進むことへの期待
- (2)理科に関わる子どもの興味・関心への対応
- 3.家庭における理科・科学に関わる活動の取り組み
- (1)理科・科学に関わる活動の取り組み状況
- (2)家庭の特性と理科・科学に関わる活動の機会
- おわりに
- »第3章 どのような子どもが理科を好きになるのか
- はじめに
- 1.「理科好き」を伸ばす子どもの性格・行動特性
- (1)「理科好き」な子は、どのような性格・行動特性を持っているか?
- (2)「理科好き」の資質とは?
- (3)「理科好き」な子は、理科の勉強も得意?
- (4)理科が好きな子は、どんな教科が好き?
- 2.どのような環境が子どもの「理科好き」を育むのか?
- (1)都会に住む子より、地方に住む子のほうが「理科好き」?
- (2)どのような地域特性が、子どもの「理科好き」を支えるのか
- 3.子どもの「理科好き」を支える、家族のかかわり方
- (1)子どもの理科的な興味・関心に理解を示す大人の家族の存在
- (2)子どもの理科的な興味・関心に対する、大人の家族のつきあい方
- おわりに
- »おわりに